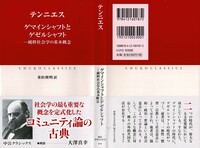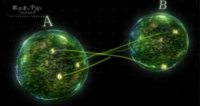原田雅樹著、『量子と非可換のエピステモロジー: 数学と物理学における概念と実在』 (Epistemology of Quantum and Noncommutativity – Concepts and Realities in Mathematics and Physics)東京大学出版会 2024年3月28日初版。(試し読みはここ)
原田雅樹著、『量子と非可換のエピステモロジー: 数学と物理学における概念と実在』 (Epistemology of Quantum and Noncommutativity – Concepts and Realities in Mathematics and Physics)東京大学出版会 2024年3月28日初版。(試し読みはここ)
去年秋、たまたま書店で見つけ、妙に惹かれ即座に購入した。著者の原田雅樹氏が、カトリック司祭でもあると、後から知った。カトリック聖職者で量子基礎論を研究するひとに、またひとり邂逅した。
本書には、カトリック司祭でありながら神学的議論を夾まない意図が感じられる。淡々と数式、数学概念、物理概念、哲学概念が展開される。しかし著者のカトリック司祭としての「思い」は垣間見える。たとえば2頁目、赤で示した部分にその「思い」が表れている。
なお、存在論(ontology)と認識論(epistemology)は、通常の西洋哲学においては、根幹で対立しあう概念。つまり、本質存在(onto)があるから「私」は在るのか、「私」が認識(epistanai)するから「私」は在るのか、が長く対立している。このことを念頭に置いて、以下読んで頂きたい。
序 2. エピステモロジー
本書は、フランス・エピステモロジーを紹介しつつ、その他の哲学的立場、特に解釈学的現象学との関連性を示し、そこで導入された方法論を20世紀の物理学、数理物理学、数学に適用しようとするものである。エピステモロジーは、存在論に対する認識論を通常は意味する。しかしフランス哲学の文脈では科学史と結びついた科学認識論に近い意味を有し、そう訳されることも多い。ただし、科学史と言っても、科学と政治史ないし社会史の関係を研究する外的歴史ではなく、科学内部の概念の発展史を研究する内的歴史と結びついた科学認識論である。
エピステモロジーとは何であるのか。金森修は、岩波の『哲学思想事典』の「エピステモロジー」の項目で次のように述べている。
〔エピステモロジーは、〕現在ではコントあたりを淵源とするフランスの合理主義的、主知主義的、分析的な科学哲学を指すために使用されることが多い。ただ英米系の論理実証主義が、形式言語による科学理論の論理的再構成を主眼としたのに対して、伝統的に科学史と深い関係を保つという特徴をもつ。個別科学の具体的事実の史的分析をする過程で、科学理論を構成するうえで内容的に原理的重要性をもつと考えられる概念を幾つか抽出する。例えば無限、エントロピー、原子、進化などである。そのうえでそれらの概念が理論内に組み込まれていく際の歴史的文脈を克明に辿りながら、組み込み前後における説明機構の変遷を分析して、当の概念が果たす役割を浮き彫りにする。それは生成過程の科学思考の歴史的分析だといえる。〔……〕エピステモロジーは個人を超える非人格的知識がもちうる存在様態を付随的に明らかにするという意味あいをもつ。それは、超越論的主体による意識的な世界構成を基盤におく現象学的哲学と多くの点で対立する。1960年代にフランス思想界を席捲した構造主義もエピステモロジーとの関連のなかで理解される必要がある。
『哲学思想事典』1993、p.161
私(齋藤旬)の勝手な読みだが、ひょっとしたら原田師は、ontological epistemology(存在論的認識論)といったような概念を提唱しようとしているのではないか。つまり、本質存在(onto)があり、それを「私」が認識(epistanai)するから「私」が在る、といったような考え方を打ち出そうとしているのではないか。(Ngramで調べると、ontological epistemologyという用語の初出は1916年。量子力学が萌芽していく時期。何か関係がありそうだ。)
また、私はカトリックだが物理学が専門で、哲学用語には疎い。なので読解にAI活用が便利。たとえば35頁:
(3)カントによる数学論と哲学の方法
数学における直示的方法 カント(Immanuel Kant, 1724-1804)の哲学は、ニュートン物理学がどうして正当化できるかという問題を射程の一つにおき、それが超越論的演繹を実行する一つの大きな動機となっている7)。カントは、『純粋理性批判』のA版を著した後、そしてB版を著す前に『自然科学の形而上学的諸原理』を著している。ヴュイユマンは『カントの物理学と形而上学』(Vuillemin [1955])で、この二つの著作を関連付けて読み込んでいるが、それは、そのような読解を与えることで、フランスの反省哲学のような、カント哲学に対する極度に観念論的な解釈を避けるためである。
カント哲学では、ア・プリオリな総合判断の上に成立する知に数学といわゆる数理物理学がある。そしてカントは、数学と物理学をはっきりと区別してはいるものの、その間にある深い連関について考えている。ヴュイユマンの『カントの物理学と形而上学』第1章は、カントの物理学と数学について扱っており、その第1節は「直観と存在」と名付けられている。カントは『自然科学の形而上学的諸原理』の中で、特定された自然的諸物に関する純粋自然論は、自然一般に関わる純粋哲学と区別されたものであり、この特定化のためには数学による概念の構成が必要であると述べる。この数学による概念の構成には、直観が深く関わっている。他方、数学によって特定された純粋自然論、すなわち数理物理学は、対象の存在に関わるために、形而上学的諸原理を必要とする(Kant, MAN, カッシーラー版C.347, p.12)。この形而上学的諸原理こそが、構成された数学概念にそれが適用されるための実在的対象を与え、それによって数理物理学を可能にする。
__________
7) カントにおける超越論的演繹とは事実問題ではなく、権利問題に関わり、カテゴリーの客観的妥当性を証明する議論のことである。「カントの言う『演繹』は、帰納に対して演繹と通常言われるもの、すなわち一般的な命題から特殊的な命題を三段論法的な推論によって論理的に正しく導出する手続きを意味するものではない。〔・・・・・・〕カント独特の『演繹』とは、〔・・・・・・〕人間が世界において行う認識や道徳的な行為、美的並びに目的論的な判定といった広義の経験の諸領域における最高の原理を確立する事によって、そうした諸領域を正当化し根拠づけるという哲学本来の課題を果たすために、カントが案出した議論の形式であった」(『カント事典』、p.39)。
カッシーラーの名前は、この部分も含めて全編にわたり9箇所出てくる。このことから、本書が属する哲学をドイツ哲学で分類すれば、ニュートン力学とユークリッド幾何学を基盤とする決定論的Kantian philosophy(カント哲学)ではなく、量子力学と相対性理論(リーマン幾何学)を基盤とする非決定論的Neo-Kantian philosophy(新カント哲学)であることが分かる。何故ならカッシーラーこそが、1937年著書『決定論と非決定論』において、量子力学と相対性理論(リーマン幾何学)を基盤とする非決定論的Neo-Kantian philosophy(新カント哲学)を創始したからだ。
p.p.297-301の「あとがき――登場人物とその周辺、そして痛切な現実」では、著者のカトリック司祭としての側面も垣間見える。そこには、本ブログ記事のタイトルにした湯川秀樹氏の短文も配されている。転記しておく。
真実
現実は痛切である。あらゆる甘さが排斥される。現実は予想できぬ豹変をする。あらゆる平衡は早晩打破せられる。現実は複雑である。あらゆる早合点は禁物である。
それにもかかわらず現実はその根底において、常に簡単な法則に従って動いているのである。達人のみがそれを洞察する。
それにもかかわらず現実はその根底において、常に調和している。詩人のみがこれを発見する。
達人は少ない。詩人も少ない。われわれ凡人はどうしても現実にとらわれすぎる傾向がある。そして現実のように豹変し、現実のように複雑になり、現実のように不安になる。そして現実の背後に、より広大な真実の世界が横たわっていることに気づかないのである。
現実のほかにどこに真実があるかと問うことなかれ。真実はやがて現実となるのである。
昭和16年1月
湯川秀樹『目に見えないもの』(講談社、1977年)より