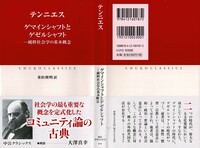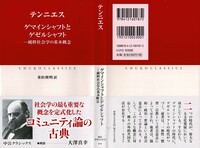 1887年初版、1912年改訂増補版、テンニエス『ゲマインシャフトとゲゼルシャフト』。その重松俊明氏による抄訳 河出書房新社1963年初版が、中公クラシックスから先月、新たな解説と索引つきで改版刊行された。カバーと帯を左掲。(全訳は、岩波文庫1957年 杉之原寿一 訳 上下巻がある。)
1887年初版、1912年改訂増補版、テンニエス『ゲマインシャフトとゲゼルシャフト』。その重松俊明氏による抄訳 河出書房新社1963年初版が、中公クラシックスから先月、新たな解説と索引つきで改版刊行された。カバーと帯を左掲。(全訳は、岩波文庫1957年 杉之原寿一 訳 上下巻がある。)
当ブログのタグ「新たな社会経済システム」の意味を理解する上で必要になる基礎概念の幾つかが、本書によって19世紀終わりに整理された。
中公クラシックス版で新たに付された大澤真幸氏による解説「社会学史上最も重要な概念」は、①テンニエスの略歴、②『ゲマインシャフトとゲゼルシャフト』の要約、③見田宗介氏による概念発展、④大澤真幸氏による仮説的発展、からなる。
そのうち、②『ゲマインシャフトとゲゼルシャフト』の要約、および、④大澤真幸氏による仮説的発展、これらを以下に転記しておく。
②『ゲマインシャフトとゲゼルシャフト』の要約
互いの意志や身体を保持し合う相互肯定的な関係には二つの種類がある。テンニエスはこの様に論ずる。それらがゲマインシャフトとゲゼルシャフトである。ゲマインシャフトとは「有機的な生命体」と見なされる集団であり、ゲゼルシャフトとは「機械的な構成体」と見なされる集団である。
こうしたゲマインシャフトとゲゼルシャフトの違いが、諸個人を結びつけている意志の相異に対応していると見たところに、テンニエスの独創性がある。ゲマインシャフトは「本質意志」に基づいている。すなわち、個人達は、「あらゆる分離にもかかわらず本質的には結合している」。それに対して、ゲゼルシャフトは「選択意志」に基づいている。すなわち、個人達は、「あらゆる結合にもかかわらず本質的には分離している」。もう少しわかりやすく言い換えよう。ゲマインシャフトは、無条件の信頼に満ちた親密な共同生活のことである。それに対して、まずは相互に独立した個人がいて、それらの個人がそれぞれの目的や利害に基づいて選択的(戦略的)に結びついたことで形成される、機械的で、人工物のような集合体がゲゼルシャフトだ。
本訳書に見られるように、「ゲマインシャフト」「ゲゼルシャフト」と、ドイツ語をそのままカタカナで表記して使われるのは、それぞれの概念のニュアンスを正確に伝える日本語がないからである(「共同社会」「利益社会」等と訳されたこともあるが、日本語として不自然な上に、不正確な翻訳。)ちなみに、英語では、ゲマインシャフトが”community”、ゲゼルシャフトが”society”と訳されるのが普通だが、この場合も、ドイツ語の方に本来あった含みがいくぶんか失われている。
テンニエスは、ゲマインシャフトを、「家族(血縁社会)/村落(地縁社会)/都市(友情社会)」の三段階に区分している。それぞれに対応する社会意志は、「民族/自治共同体/教会」である。
ゲゼルシャフトの方は、「大都市/国民/世界」の三段階に区分される。この三段階に対応する社会意志は「協約/政治/世論」だとされ、それらを担う本来の主体は「ゲゼルシャフトそのもの/国家/学者共同体」である。
④大澤真幸氏による仮説的発展
ここから思い切って踏み込んで、さらに次の様に言うことも出来るかもしれない。任意の人間の社会は、ゲマインシャフト性とゲゼルシャフト性を含んでいる、と。ゲマインシャフトとゲゼルシャフトは、排他的な社会の分類というよりも、人間の社会を形成する二つの力のようなものではないか。その中に含んでいる二つの力の配分には多様性があるが、ゲゼルシャフト的な側面を完全に排除したゲマインシャフトもなければ、ゲマインシャフト的な基礎を全くもたないゲゼルシャフトも存在しない。このように考えることも出来るかもしれない、ということをここで仮説的に提案しておこう。
つまり人間社会はゲマインシャフトでもあり、ゲゼルシャフトでもある。この二律背反的な状態が極端に先鋭化して現れるようになったのが近代社会ではないか。一方では、厳密には個人の集合だけがあり、「社会」なる実体はどこにも存在しない、とも言える。しかし、他方では、社会は有機体のようなまとまりを持ち、個人とは独立して存在している「事実」があって、個人の意識や行動を規定している、とも見なしうる。どちらも真実である。この対立的な事象のどちらもが真実であることが明らかになったとき、社会学という知が成熟したのではあるまいか。実際、この二つは、社会学を規定する二つの代表的な方法論的な立場に対応している。
古典的な通常の解説の範(のり)を超え、その後の発展や、さらには仮説的なことまでごく簡単に述べてみた。「ゲマインシャフトとゲゼルシャフト」がいまなお生きた概念であり、発展途上にある、ということを示唆したかったからだ。そして、この発展の根の部分には、テンニエスが若き日に著した本書がある。 (おおさわ・まさち 社会学者)